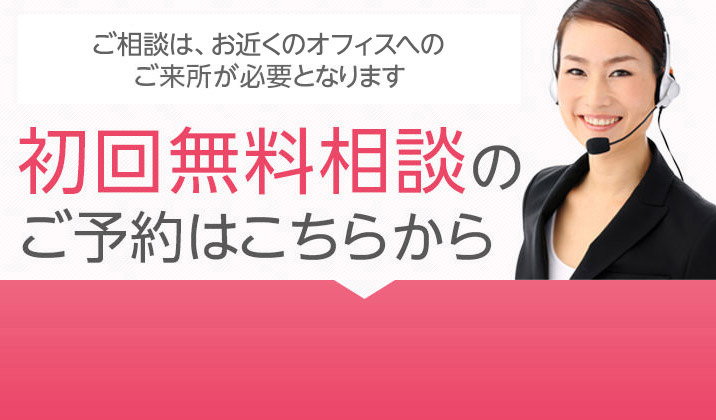離婚調停を申し立てられたらやるべきこと|調停の流れとポイント
- 離婚
- 離婚調停
- 申し立てられた

裁判所が公表している司法統計によると、令和3年に東京家庭裁判所に申立てのあった「婚姻中の夫婦間の事件」に関する調停件数は、4535件でした。多くの離婚事件が裁判所で扱われていることがわかります。
離婚の話し合いで揉めていると、相手から離婚調停を申し立てられることがあります。突然、裁判所から調停の申立書や期日の通知書が届くと、動揺してしまう方も多いでしょう。しかし、有利な条件で離婚をするためにも、離婚調停の期日までにしっかりと準備を進めておくことが大切です。
今回は、配偶者から離婚調停を申し立てられた場合の対策と注意点について、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそも離婚調停とはどのような手続き?
そもそも離婚調停とはどのような手続きなのでしょうか。
-
(1)離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所を介して、夫婦が離婚について話し合いを行う手続きです。
離婚をする際、まずは、夫婦の話し合いによって離婚の成立を目指します。これを協議離婚といいます。しかし、当事者だけの話し合いでは、感情的になったり、言い合いになったりして、スムーズに話し合いを進めることができないことも少なくありません。
離婚調停は、家庭裁判所の裁判官や調停委員という第三者を介して話し合いが行われるため、夫婦だけでは話し合いが難しいケースでもスムーズな進行が期待できます。 -
(2)離婚調停の流れ
離婚調停の申立てから成立までは、一般的に以下のような流れで進みます。
① 離婚調停の申立て
離婚調停をするには、まずは、家庭裁判所に離婚調停の申立書および戸籍謄本などの必要書類を提出します。提出先の家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める過程裁判所(家事事件手続法245条1項)です。
② 調停期日の決定
調停の申立てが受理されると、裁判所が初回の調停期日の日時を決定し、相手方に調停申立書と調停期日通知書を送付します。初回の調停期日は、申立てからおおよそ1か月後ですが、申立人と裁判所の都合を踏まえて決定されるため、調停を申し立てられた当事者(相手方)は予定によって初回の調停期日に出席できないこともあります。しかし、3章で後述するように無断欠席にはリスクがありますので注意しましょう。
③ 第1回調停期日の開催
裁判所に決められた日時に家庭裁判所に出向いて、第1回調停期日を行います。調停では、男女1名ずつの調停委員と裁判官によって構成される調停委員会が主催して行いますが、実際の進行は調停委員が行います。
当事者は、それぞれ申立人待合室・相手方待合室で待機して、調停委員から呼ばれたら調停室に入り、話をすることになります。申立人と相手方は交互に呼ばれて話を聞かれますので、調停でお互いが顔を合わせて話し合いをすることは基本的にはありません。
初回の調停期日で合意が成立しなかった場合は、次回の調停の日程を決めて終了となります。
④ 2回目以降の調停期日の開催
2回目以降の調停も初回調停と同様の形式で話し合いが進められていきます。調停は、1か月から1か月半に1回のペースでしか行われませんので、解決まではある程度の時間を要することになります。
⑤ 調停の成立または不成立
調停による話し合いの結果、離婚および離婚条件について合意が成立した場合には、調停成立となります。
当事者が合意した内容は、調停調書という書面にまとめられます。申立人は、10日以内に離婚届と調停調書を市区町村役場に提出しなければなりません。
離婚届を提出しなければ戸籍上は離婚したことになりませんので、必ず提出が必要です。なお、調停調書は郵送で受け取る場合、1~2週間ほどで届きますが、調停成立から10日以内に離婚届を提出するために、直接裁判所に受け取りに行った方がよいでしょう。
調停による話し合いで合意できなかった場合、調停は不成立となります。その後も離婚を希望する場合には、裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
この場合、裁判所に調停不成立証明書の交付を申請して取得することになります。なお、調停が不成立となった場合でも、当事者双方の趣旨に反しないことを考慮して離婚が妥当だと判断できた際に、裁判所の判断で離婚の審判が下されることもあります(審判離婚)。
2、離婚調停を申し立てられたらやるべきこと
配偶者から離婚調停を申し立てられた場合には、以下のような対応が必要になります。
-
(1)スケジュール調整
初回の調停期日は、申立人と裁判所の都合によって決められますので、指定された期日とスケジュールが合わないことも珍しくありません。
スケジュールの調整が難しい場合には、家庭裁判所に欠席する旨の連絡をします。無断欠席は、3章で後述するようなリスクがありますので絶対に避けましょう。 -
(2)離婚に関する自分の考えをまとめる
離婚調停の申立書には、申立人が希望する離婚条件と離婚に至る動機が簡単に記載されています。詳細な理由や離婚条件については、初回の調停期日で聞くことになりますので、申立書の内容を踏まえて、以下のような希望を考えておきましょう。
- 離婚に同意するか拒否するか
- 離婚する場合、親権や財産分与などの条件をどうするか
ある程度具体的な内容をまとめておくことで、調停期日での話し合いをスムーズに進めることができます。
-
(3)答弁書を期日までに提出する
裁判所からは、離婚調停の申立書と調停期日通知書のほかに、以下のような書類が含まれています。
- 答弁書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 連絡先等の届出書
調停を申し立てられた方は、これらの書類に必要事項を記載して、期限までに裁判所に提出するようにしましょう。特に、答弁書は、調停委員に対して自分の考えを伝えるための重要な書類になりますので、よく考えてから記入してください。
答弁書の形式は、裁判所によって多少異なりますが、簡単なチェック式であることが多いです。チェック式では十分な意見が伝わらない場合には、「別紙のとおり」として、別の用紙に自分の意見を記載したものを提出することも有効です。
3、離婚調停の呼び出しを無視した場合のリスク
離婚調停の呼び出しを無視した場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
-
(1)離婚調停を無視した場合のリスク
調停は、話し合いの手続きですので、一方の当事者が調停を欠席していると話し合いを進めることができません。裁判のように欠席したからといって、一方的に不利な内容で調停が成立するということはありませんが、無断欠席には以下のようなリスクがありますので注意が必要です。
① 裁判官や調停委員に悪い印象を与える
調停期日を無断で欠席した場合には、裁判官や調停委員に対して、「約束を守らない人」、「ルーズな人」といった悪い印象を与えてしまいます。調停は、裁判官や調停委員が主催して、紛争の調整をしてくれますので、その人に対して悪い印象を与えてしまうと、調停委員を味方に付けることができず、調停を有利に進めることができません。
② 調停が不成立になる
初回期日を欠席したからといってすぐに調停が不成立になるわけではありませんが、何度も無断欠席を繰り返していると、話し合いによる解決の見込みがないとみなされて調停が不成立になってしまいます。
調停が不成立になると相手から離婚訴訟を提起されることになります。しかし、離婚訴訟は、離婚調停のような話し合いの手続きではありませんので、柔軟な解決ができず、場合によっては、調停で解決する場合に比べて不利な内容になってしまう可能性もあります。
③ 過料の制裁を受けるリスクがある
正当な理由なく調停期日に出席しない場合には、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(家事審判法27条)。実際に過料の制裁を受けることはほとんどありませんが、リスクとしてゼロではありませんので注意が必要です。 -
(2)離婚調停に出席できない場合の対応方法
初回の離婚調停に出席できない場合には、裁判所から送られてきた書類に含まれる「進行に関する照会回答書」に、初回期日は出席できないと記載して裁判所に送りましょう。そうすると、2回目の調停期日の日程を決めるために裁判所から連絡が来ますので、裁判所との間で2回目の調停期日の調整を行います。
2回目以降の離婚調停は、当事者の都合を確認した上で日程が決められますので、原則として出席することが求められます。しかし、どうしても外すことができない予定が入ってしまったという場合には、裁判所に連絡をすれば、日程変更などに応じてもらえる可能性があります。
4、離婚調停を申し立てられた場合、弁護士に依頼するメリット
配偶者から離婚調停を申し立てられた場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。
-
(1)答弁書の作成をサポートしてもらえる
調停委員に自分の意見や主張を理解してもらうためには、あらかじめ答弁書に具体的な事情を記載して提出することが大切です。調停期日に調停委員に口頭で説明することもできますが、限られた時間の中ですべてを伝えることは難しく、口頭だけの説明では調停委員に伝わりにくいこともあるでしょう。
事前に答弁書を提出しておけば、裁判官や調停委員も目を通したうえで臨むため、争点に絞った効率的な話し合いを行うことができます。弁護士に依頼をすれば、答弁書の作成をサポートしてもらえるため、より効果的に自分の意見や主張を伝えることができます。 -
(2)期日に同席してサポートしてもらえる
弁護士に依頼をしたとしても、離婚調停の期日には、当事者本人の出席も原則として必要となります。しかし、弁護士に依頼をすれば調停期日に同席をしてもらい、調停委員と話をする際にもサポートを受けることができます。
初めての調停では、どうしても緊張してしまい調停委員にうまく自分の意見や主張を伝えることができないことも少なくありません。そのような場合でも弁護士のフォローがあれば安心して話をすることができるでしょう。
5、まとめ
配偶者から離婚調停を申し立てられたという場合には、初回の調停に向けて準備を進めていく必要があります。有利に調停を進めるためには、事前準備を行うことが大切ですので早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚調停を申し立てられたという方は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|