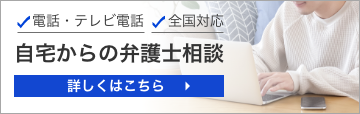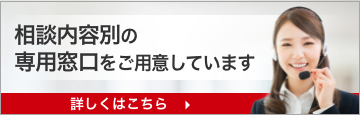景品表示法の優良誤認とは何か。違反したらどうなる?
- 一般企業法務
- 景品表示法
- 優良誤認

景品表示法(景表法)では、優良誤認表示などの不当表示が禁止されています。
景品表示法に違反する広告表示などを行うと、内閣総理大臣による措置命令や課徴金納付命令などを受けることがあるので注意が必要です。
本記事では、景品表示法による優良誤認表示などの不当表示規制について、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。
1、景品表示法とは? 優良誤認表示とは?
景品表示法は、事業者による不当な景品類の提供や不当表示によって、一般消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害される事態を防ぐための規制を定めた法律です。
優良誤認表示は、景品表示法に基づく不当表示の一つとして禁止されています。
-
(1)景品表示法の目的
景品表示法の目的は、事業者による不当な景品類の提供や不当表示によって、一般消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害される事態を防ぐことです(同法第1条)。
事業者があまりにも高額の景品類を「おまけ」として提供すると、一般消費者がそれにつられて、品質や価格などとは無関係に商品やサービスを選択してしまいます。
また、事業者が実態にそぐわない広告などの不当表示をしていると、一般消費者はそれにだまされて、粗悪な商品やサービスを購入してしまうおそれがあります。
このような事態は、一般消費者の利益を不当に害するものといえます。景品表示法では、これらの事態を防ぐために必要な規制を設けています。 -
(2)景品表示法による規制の内容
景品表示法による規制内容は、以下の2点に大別されます。
① 景品類の制限および禁止
景品類について、最高額・総額・種類・提供方法などに関する規制が設けられています。
参考:「景品規制の概要」(消費者庁)
② 不当な表示の禁止
事業者が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示が禁止されています。
参考:「表示規制の概要」(消費者庁) -
(3)優良誤認表示とは
優良誤認表示は、景品表示法によって禁止されている不当表示の一つです。
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質などについて、実際のものよりも著しく優良、または事実に相違して競合他社のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものをいいます(景品表示法第5条第1号)。
一般消費者が実態にそぐわない広告などにだまされて、不本意に表示内容よりも粗悪な商品やサービスを購入してしまう事態を防ぐため、優良誤認表示が禁止されています。 -
(4)優良誤認表示の具体例
優良誤認表示に当たる表示としては、以下のような例が挙げられます。
- カシミヤが80%程度しか含まれていないセーターにつき、「カシミヤ100%」と表示した
- 「日本国内で唯一、X技術を採用した画期的製品」と表示していたが、実際には競合他社もX技術を用いて製造した製品を販売していた
2、景品表示法に基づく、優良誤認表示以外の不当表示
景品表示法では、優良誤認表示以外に「有利誤認表示」と「その他の不当表示」を禁止しています。
-
(1)有利誤認表示
有利誤認表示とは、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものまたは競合他社のものよりも著しく有利である一般消費者に誤認させる表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものをいいます(景品表示法第5条第2号)。
一般消費者が「安い」「お得だ」などと思って商品やサービスを購入したところ、実際には得をしていなかったなどの事態を防ぐため、有利誤認表示が禁止されています。
有利誤認表示に当たる表示としては、以下のような例が挙げられます。- 「先着100名のみ5割引で購入可能」と表示して商品を販売していたが、実際には100名を超える購入者全員に対して「5割引」の価格でその商品を販売していた
- 「料金が通常の半額」と表示して商品を販売していたが、実際には通常と同じ料金だった
-
(2)その他の不当表示
優良誤認表示と有利誤認表示のほかにも、景品表示法では以下の不当表示を禁止しています。
① 無果汁の清涼飲料水等についての表示
(例)果汁又は果肉を使用していないことが表示されないままパッケージに果実の絵が表示されているのに、実際には果汁が使用されていなかった
② 商品の原産国に関する不当な表示
(例)日本国内で生産されているのに、アメリカ国旗を用いてアメリカ原産であるかのように表示していた
③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
(例)消費者金融の利息について、税引き前の年率だけが表示されており、税引き後の実質年率が表示されていなかった
④ 不動産のおとり広告に関する表示
(例)販売するつもりがない不動産の広告を掲載し、問い合わせがあった際には別の不動産の購入を勧誘していた
⑤ おとり広告に関する表示
(例)回転寿司店が全店舗で「まぐろフェア」を開催する旨の広告を掲載したものの、実際にまぐろを用いた商品が提供された店舗はごく一部だった
⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示
(例)入居者はフィットネスジムをいつでも利用できるとうたった広告がなされていたものの、実際には利用するたびに料金を支払う必要があることが表示されていなかった
⑦ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(いわゆる「ステルスマーケティング」)
(例)インフルエンサーに対して報酬を支払い、広告である旨を隠してPRをしてもらった
お問い合わせください。
3、景品表示法に違反した場合のペナルティー
事業者が景品表示法違反に当たる不当表示をすると、以下のようなペナルティーを受けることになりかねません。商品やサービスの広告などを行う際には、景品表示法の規制の順守を徹底しましょう。
-
(1)措置命令
事業者による不当表示を認定した場合、内閣総理大臣は違反事業者に対して、不当表示の差止めや再発防止のために必要な事項などを命ずることができます(=措置命令。景品表示法第7条)。
たとえば2024年8月には、スポーツジムなどを運営する会社に対して、Instagram(インスタグラム)上の投稿が優良誤認表示およびステルスマーケティングに当たることを理由に、一般消費者に対する周知徹底や再発防止策の徹底などが命じられました。
出典:「RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁) -
(2)課徴金納付命令
優良誤認表示または有利誤認表示をした事業者に対して、内閣総理大臣は課徴金納付を命じなければなりません(景品表示法第8条)。
たとえば2024年5月には、電力供給事業を運営する会社に対して、電気料金が安価になるとうたう表示が有利誤認表示に当たることを理由に、16億5594万円の課徴金の納付が命じられました。
出典:「中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(消費者庁)
課徴金の額は原則として、対象となる不当表示がなされていた期間中の売上の3%相当額です。ただし、不当表示を自主的に報告した場合は、課徴金が2分の1に減額されることがあります(同法第9条)。また、一般消費者に対する返金措置を行った場合は、返金額が課徴金の額から控除されます(同法第10条、第11条)。 -
(3)刑事罰
優良誤認表示または有利誤認表示をした者は「100万円以下の罰金」に処されます(景品表示法第48条)。また、法人に対しても両罰規定によって「100万円以下の罰金」が科されます(同法第49条第1項第2号)。
これらの罰則規定は、2024年10月1日から新たに施行されました。
また、消費者庁長官の措置命令に違反した者は「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に処され、または拘禁刑と罰金が併科されます(同法第46条)。さらに措置命令違反については、法人にも両罰規定によって「3億円以下の罰金」が科されます(同法第49条第1項第1号)。 -
(4)社会的信用の喪失
景品表示法違反によって措置命令や課徴金納付命令を受けた場合、消費者庁のサイトで公表されます。
不当表示をしていた事実が大々的に公表されれば、企業としての社会的信用を失い、売上や人材採用などに悪影響が生じるおそれがあるので要注意です。
4、企業が顧問弁護士と契約するメリット
顧問弁護士は、広告内容のリーガルチェックを行い、景品表示法違反によって措置命令や課徴金納付命令を受けるリスクを防ぎます。また、景品表示法に関する事柄以外にも、従業員との労働問題、SNS企業アカウントの運用、契約書のリーガルチェックなど、さまざまな事柄について相談可能です。
特にコンプライアンスの強化を検討している企業は、顧問弁護士との契約をご検討ください。
5、まとめ
商品やサービスの広告などを行う際には、品質や価格などについて実態に沿った表示をすることが大切です。誇大広告をすると、消費者庁から優良誤認表示、有利誤認表示などの景品表示法違反を指摘され、措置命令や課徴金納付命令を受けてしまうおそれがあります。
景品表示法違反を防ぐためには、広告などについて弁護士のリーガルチェックを受けるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、景品表示法に関する企業のご相談を随時受け付けております。また、ニーズに応じてリーズナブルにご利用いただける顧問弁護士サービスもご利用可能です。
広告表示に関するコンプライアンスを強化したい企業や、顧問弁護士をお探しの企業は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています