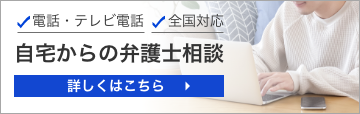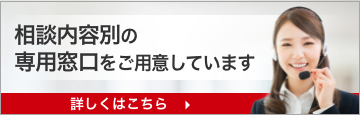カスハラ対策で条例が施行? 法律での規定とともに解説
- 一般企業法務
- カスハラ
- 条例

飲食店や施設の従業員などに対して、顧客等が理不尽な迷惑行為をする「カスハラ(カスタマー・ハラスメント)」が横行しています。この状況を受けて、東京都では有識者らによる検討部会が設置され、全国初のカスハラ防止条例が制定されました。
令和7年4月1日に施行された東京都カスタマー・ハラスメント防止条例には、罰則規定はありませんが、カスハラに対しては現行法下でも刑法や民法が適用され、その内容によっては犯罪や不法行為に該当します。企業としては、カスハラに関する法律のルールを理解して、いつでもカスハラ顧客等に対抗できる体制を整えましょう。
本記事ではカスハラに関する法規制について、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士が解説します。
1、カスハラとは
「カスハラ」とは「カスタマー・ハラスメント(customer harassment)」の略称で、顧客等が、企業などの従業員等に対して、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって就業環境を害するものをいいます(上記条例参照)。
-
(1)カスハラが増加した背景
カスハラが増加した要因としては、SNSや口コミサイトの普及によって顧客側の発言力が増大したことが挙げられます。
インターネット上に悪評が書き込まれることは、企業側にとって脅威です。
SNSや口コミサイトを通じて、顧客側が手軽な方法で企業にダメージを与えることができるようになり、企業側がその顧客側の要望に応じてしまうという状況が生じやすくなったため、顧客側の要求が理不尽化する傾向が強まっています。
また、多種多様なハラスメントが取り沙汰される近年の風潮も相まって、カスハラの問題点がいっそうクローズアップされています。 -
(2)正当なクレームとカスハラの違い
カスハラは、顧客等からの正当なクレームと区別する必要があります。
正当なクレームに対しては真摯(しんし)に向き合い、カスハラに対しては毅然(きぜん)とした態度で要求を拒否するというように、対応を使い分けることが大切です。
正当なクレームとカスハラの区別は、以下の2つの観点から判断します。- 要求内容の妥当性
- 要求を実現するための手段・態様の相当性
そもそも要求の内容自体に妥当性がない場合は、正当なクレームではなくカスハラと判断すべきです。自社の側に全く落ち度がなく、純粋に顧客の都合だけで便宜を図るように求めてきたら、カスハラとして対処しましょう。
また、要求の内容が妥当であっても、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当である場合もカスハラに当たります。たとえば、商品の不備について店員に土下座を要求する行為などが典型例です。
要求の内容が妥当であり、かつその要求を実現するための手段・態様も社会通念上相当である場合に、初めて正当なクレームとなります。正当なクレームは真摯に聞き入れて、会社としてどのように対応すべきかを検討しましょう。 - 要求内容の妥当性
2、カスハラについて成立する犯罪
カスハラは、その態様によっては犯罪に該当し、罰則の対象となることがあります。犯罪に該当するカスハラについては、警察に通報すれば対応してもらえる可能性が高いです。
カスハラについて成立する主な犯罪は、以下のとおりです。
-
(1)暴力を振るった場合|暴行罪・傷害罪
顧客等が施設の従業員などに対して暴力を振るったときは、被害者にケガがなければ暴行罪(刑法第208条)、被害者がケガをすれば傷害罪(刑法第204条)が成立します。
暴行罪・傷害罪の法定刑は以下のとおりです。暴行罪 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 傷害罪 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 -
(2)誹謗中傷をした場合|名誉毀損罪・侮辱罪
顧客等が企業、店舗・施設、従業員などに対して誹謗中傷をした場合において、公然と何らかの事実を摘示して社会的評価を低下させたら「名誉毀損罪」(刑法第230条)、事実の摘示なく公然と侮辱をしたら「侮辱罪」(刑法第231条)が成立します。
名誉毀損罪・侮辱罪の法定刑は以下のとおりです。名誉毀損罪 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 侮辱罪 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 -
(3)脅迫をした場合|脅迫罪・強要罪・恐喝罪
顧客等が店舗や施設の従業員などに対し、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合は「脅迫罪」(刑法第222条)が成立します。
また、脅迫によって義務のないことを行わせた場合は「強要罪」(刑法第223条)、恐喝によって財物を交付させた場合は「恐喝罪」(刑法第249条)が成立します。
脅迫罪・強要罪・恐喝罪の法定刑は以下のとおりです。脅迫罪 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 強要罪 3年以下の拘禁刑 恐喝罪 10年以下の拘禁刑 -
(4)会社の業務を妨害した場合|業務妨害罪
顧客等が威力を用いて会社の業務を妨害した場合には「威力業務妨害罪」(刑法第234条)、偽計等により会社の業務を妨害した場合には「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が成立します。
威力業務妨害罪の法定刑は以下のとおりです。威力業務妨害罪 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 偽計業務妨害罪 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
お問い合わせください。
3、会社や従業員が損害を受けた場合は、損害賠償請求が可能
カスハラによって会社や従業員が損害を受けた場合には、顧客等に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法第709条)。
-
(1)損害賠償の主な対象項目
カスハラについて賠償の対象となる主な損害としては、以下の例が挙げられます。
- カスハラによって業務が停滞し、または評判が落ちたことによる売上の減少額(逸失利益)
- 会社がカスハラ対応に要した費用
- カスハラを受けた従業員の精神的損害
-
(2)損害賠償請求の手続き
カスハラ顧客等に対する損害賠償請求の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
① 顧客等の氏名・住所を把握する
店舗・施設などの現場において、顧客等から氏名や住所を聞きましょう。
② 損害賠償請求の準備を整える
会社が被った損害を集計する、カスハラに当たる言動を記録化して保存するなど、損害賠償請求の準備を整えましょう。
③ 任意交渉をする
準備が整ったら、顧客等に連絡して任意交渉を開始します。
任意交渉では、会社側で集計した損害額をベースに、顧客等に対して支払いを求める額を提示します。顧客等から対案があれば、その内容を検討し、互いに歩み寄って解決を目指します。
任意交渉がまとまったら、その内容を合意書にまとめた上で、会社と顧客の間で締結しましょう。
④ 損害賠償請求訴訟を提起する
任意交渉でまとまらない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
損害賠償請求訴訟では、会社側が不法行為の要件をすべて立証しなければなりません。カスハラに当たる言動や被った損害に関する証拠を、できる限り豊富に集めて提出しましょう。
⑤ 強制執行を申し立てる
訴訟の判決にて賠償額が確定すると、裁判所に強制執行を申し立てることができます。顧客等が判決確定のあと任意に賠償金を支払わない場合は、強制執行によって賠償金の回収を図りましょう。
4、カスハラ対応は弁護士にご相談を
カスハラ顧客等への適切な対応を怠ると、精神的に傷ついた従業員の離職につながったり、従業員から企業に対して使用者の安全配慮義務違反であるとして損害賠償を請求されたりするおそれがあります。
カスハラから従業員を守るためには、企業として、法的な観点から毅然とした対応をとるべきです。そのためには、顧問弁護士と契約することをおすすめします。
顧問弁護士と契約すれば、カスハラ顧客等への対応方針に関して、注意すべきポイントにつきいつでも助言を受けられます。また、その他の事業運営に関する疑問点が生じた場合にも、顧問弁護士へスムーズに相談可能です。
ベリーベスト法律事務所では、不動産やエンタメ業界、ITに飲食、流通など、幅広い業種の商習慣に応じた法務サービスを提供しています。顧問弁護士との契約をご検討の際は、まずはお気軽にご相談ください。
5、まとめ
カスハラは、その内容によっては犯罪や不法行為に該当します。企業はカスハラ顧客等に対して、刑事告訴や損害賠償請求などの法的な手段で対抗することが可能です。
カスハラ顧客等に毅然と対応することは、企業としての信頼や従業員を守るという観点から非常に重要です。顧問弁護士と契約すれば、カスハラ対応の方針や注意点などについて、いつでも的確なアドバイスを受けることができます。
ベリーベスト法律事務所は、カスハラ対応に関する企業のご相談を随時受け付けております。店舗や施設などにおけるカスハラ顧客等への対応に悩んでいる企業や、カスハラに対抗するための準備をあらかじめ整えておきたい企業は、まずはベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています